- インデックス投資はカモ?
- カモにならないためにはどうすればいい?
- インデックス投資のメリットは?
初心者からベテランまで幅広い投資家に支持されているインデックス投資。
手軽で低コストな投資方法として人気のインデックス投資ですが、カモになってしまうリスクも存在します。
結論から言うと、以下のような場合はカモになってしまう可能性が高いです。
【カモになってしまう主なケース3選】
- 暴落時に売ってしまう
- 短期での成果を求める
- 投資先について理解していない
本記事では、インデックス投資はカモと言われる理由やメリット、カモになってしまうケースを解説します。
なお、インデックス投資を始めるには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
| 証券会社 | 特徴 |
 SBI証券公式サイト > >> SBI証券のメリット・デメリットについて解説 | ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 |
 楽天証券公式サイト > >> 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 | 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天カードで投資信託のクレカ積立が可能 |
 マネックス証券公式サイト > >> マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 | 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 |
 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > >> 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 | auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 |
インデックス投資はカモと言われる理由
インデックス投資はカモと言われる理由は以下の4つ。
- 何も知らずに始めてしまう
- 自分で考えない投資習慣の固定化
- 必ずしも右肩上がりとは限らない
- 必ずしも安定しているとは限らない
①何も知らずに始めてしまう
「みんながインデックス投資をしているから自分も始めよう」と考える人は少なくありません。
しかし、こうした理由で始めると、相場の変動に耐えられず、特に暴落が起きたときに慌てて損切りしてしまうケースが多く見られます。
結果として、市場の動きに振り回され、本来の長期投資のメリットを享受できずに「カモ」になってしまうのです。
インデックス投資は短期間で利益を狙うものではなく、20年、30年といった長いスパンで続けることが重要です。
長期間保有することで、価格の一時的な下落による元本割れのリスクを抑え、時間を味方につけて資産を着実に増やせます。

 サイト管理人
サイト管理人暴落時に慌てて損切りをするのではなく、むしろ市場が落ち着くまで冷静に待ちましょう。
②自分で考えない投資習慣の固定化
インデックス投資は、運用ルールがシンプルでわかりやすく、初心者でも始めやすいという大きなメリットがあります。



そのため、専門的な投資知識や難しい分析を学ばなくても、すぐにスタートできるのが特徴です。
しかし一方で、インデックス投資が簡単なために、投資や経済の変化に対して無関心になりやすいという課題もあります。
金融商品や投資環境は常に変動しているため、最新の知識や情報を常にアップデートする努力が欠かせません。
市場の動向や経済指標の変化、新たに登場する金融商品や法規制の改正など、あらゆる要素が資産運用に影響を与えます。
③必ずしも右肩上がりとは限らない
米国を代表する株価指数であるS&P500や全世界株インデックスは、一時的な下落はあるも成長を続けてきました。
一方で、日経平均株価のように、1989年のバブル期に最高値をつけて以降、約30年間低迷しているケースも存在します。


全ての株価指数が常に右肩上がりで成長するわけではなく、経済や社会の状況によっては長期間にわたり停滞や低迷が続くリスクも十分にあります。



長期投資の際には、このようなリスクも念頭に置いておきましょう。
④必ずしも安定しているとは限らない
インデックスの中には、値動きが激しいものも存在します。
【値動きの激しいインデックス】
- 新興国株式インデックス
- ナスダック100
- FANG+
新興国株式インデックスは、政治リスクや通貨リスク、さらには景気の変動などの影響を強く受けやすい特徴があります。
政治情勢が不安定だったり、通貨価値が急変したりすると、株価が大きく上下する可能性が高くなります。
一方、ナスダック100やFANG+は、米国のIT・ハイテク企業が多いため、金利上昇や業績不安で株価が下落しやすい傾向があります。
特にFANG+は構成銘柄数がわずか10銘柄と少なく、特定の企業や業種への偏りが大きい点もリスク要因となります。
インデックス投資を検討する際は、どのような銘柄や業種で構成されているかを事前に確認しておくことが重要です。



インデックスの値動きの激しさには、その構成銘柄や業種の偏りが大きく影響しています。
インデックス投資のメリット
インデックス投資のメリットは以下の4つ。
- 低コストで運用できる
- 分散投資でリスクを抑えられる
- 長期運用に向いている
- 初心者でも始めやすい
①低コストで運用できる
ファンドマネージャーが個別銘柄を一つひとつ選別する必要がないのが、インデックスファンドの大きな特徴です。



たとえば、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄は、東京証券取引所があらかじめ公表しています。
そのため、運用側はこのリストに沿って投資を行えばよく、銘柄を選定するための時間や労力をかける必要がありません。
この仕組みにより、調査や分析のコストが抑えられ、信託報酬などの運用コストも自然と低くなります。
コストが低ければ、その分だけ長期的に投資家の手元に残る利益が増え、資産形成の効率が高まります。
②分散投資でリスクを抑えられる
多数の銘柄に分散投資しているインデックスなら、特定の企業や業種の不調による影響が小さくなります。
例えば、S&P500なら米国の代表的な500社に、全世界株式なら先進国から新興国まで、世界中の株式に幅広く投資します。
分散が効いていれば、一部の企業や業種が不調でも、他の銘柄がカバーし、値動きが安定しやすくなります。



ただ、すべてのインデックスが均等に分散されているわけではありません。
例えば、FANG+やナスダック100のように、ハイテク銘柄や特定の業種に比重が偏っている指数もあります。
こうした指数は成長局面で大きなリターンを期待できる反面、不調になったときの値動きは大きくなりやすい、という特徴があります。
③長期運用に向いている
株式市場は長い目で見ると経済成長や企業の利益拡大に伴って全体的に右肩上がりの傾向があります。
そのため、コツコツ積み立てを続ければ、市場全体の成長に合わせて資産が増えていく可能性が高まります。
また、日々の株価変動を気にしなくて済むので、「上がったから慌てて買う」「下がったから不安で売る」といった感情的な判断を避けられます。



精神的な負担が少なく、忙しい人や投資初心者でも続けやすいのが特徴です。
④初心者でも始めやすい
細かく分析したり、売買のタイミングを計ったりする必要がないため、投資知識が少なくても始められます。
さらに、近年では100円程度から購入できるインデックスファンドもあり、手軽に投資を始められる環境が整っています。
少額から定期的に積み立てることで、時間を味方につけた資産運用が可能になるため、忙しい方や投資にあまり時間を割けない方にも非常に適しています。



専門知識が少なくても始めやすく、かつリスク分散もしやすいのが大きな魅力と言えるでしょう。
インデックス投資はカモ?
インデックス投資はカモではない
インデックス投資は「カモ」ではなく、むしろ個人投資家にとって最も合理的な選択肢です。
【インデックス投資はカモではない理由】
- 市場全体に投資する
- 手数料が低い
- 勝率が高い
①市場全体に投資する
インデックス投資は、市場全体に投資する方法です。
全世界株式やS&P500などのインデックスファンドを通じて、市場全体の動きに連動します。
個別株の売買タイミングを狙う必要がなく、情報戦に負ける心配もほとんどありません。
過去の米国株市場は長期的に右肩上がりで、年平均7〜10%程度のリターンを記録しています。



インデックス投資なら、この市場全体の成長に乗ることができ、長期的に資産を増やしやすいのです。
②手数料が低い
イインデックスファンドは、運用コストである信託報酬が非常に低く抑えられている点が大きな特徴です。



多くは0.1〜0.2%程度の低い手数料で運用が可能です。
一方、アクティブファンドの中には年1%前後の手数料がかかるものがあります。
高い手数料がかかるアクティブファンドと比べると、長期的な投資において大きなアドバンテージになります。
③勝率が高い
インデックス投資は、アクティブ投資に対して非常に高い勝率を誇っています。
実際、アクティブファンドの約8〜9割は、インデックスファンドの成績を下回ります。


プロが膨大なデータや専門知識を駆使して銘柄を選定したとしても、インデックスファンドに勝ち続けるのは難しいのが現実です。



一方で、インデックスファンドは非常にシンプルかつ効率的です。
特定の株価指数(たとえばS&P500や全世界株式指数など)に連動するため、その指数に含まれる多くの企業に分散投資ができます。
投資先を調べたり乗り換えたりする手間なく、積立を続けるだけで堅実に資産形成できるのがインデックスファンドの魅力です。
カモになってしまう主なケース3選
【カモになってしまう主なケース3選】
- 暴落時に売ってしまう
- 短期での成果を求める
- 投資先について理解していない
①暴落時に売ってしまう
インデックス投資は「下がっても買い続ける」ことを前提に設計されています。
しかし、実際に大きな下落が起こると、「これ以上下がったらどうしよう…」という恐怖心から手放してしまう人が少なくありません。
その結果、高値で買って安値で売るという、いわゆる「カモ行動」になってしまいます。
暴落はむしろ、長期投資家にとってはバーゲンセールのようなもの。



焦って売らず、コツコツ積み立てを続けることが成功への近道です。
②短期での成果を求める
インデックス投資は、1年や2年で大きく増えるような投資ではありません。
「3年やってみたけど、全然増えない…」と感じてやめてしまう人もいますが、その後に上昇局面が来て後悔するのが典型的な失敗パターンです。
10年以上の長期スパンで見ることが前提。



市場の上下に一喜一憂せず、淡々と続ける姿勢が最終的な成果につながります。
③投資先について理解していない
どのような資産に投資するのかを理解しておくことも重要です。
インデックス投資では、オルカン(全世界株式)や、米国の代表的な株価指数であるS&P500が人気です。



当サイトではオルカンをおすすめしています。
ただ、オルカンとS&P500はそれぞれ構成銘柄や地域の分散に違いがあり、それに伴いメリット・デメリットも異なります。
【オルカンのメリット・デメリット】
✅ メリット
- 全世界に投資できる
- 世界経済の成長を享受できる
- 成長した国は自然と組み入れられる
❌ デメリット
- S&P500よりリターンは低い
- リスクの高い新興国が含まれる
【S&P500のメリット・デメリット】
✅ メリット
- リターンが高い
- 全て米国株で構成される
- 今後も米国の人口は増加する
❌ デメリット
- 米国株だけで構成される
- 新興国の成長に対応できない
もし投資先の特徴やメリット・デメリットを理解していないと、急な下落時に冷静さを失い、慌てて売ってしまうリスクが高まります。
長期で安定した資産形成を目指すためにも、投資先について十分に理解しておくことが大切です。
インデックス投資なら新NISA
インデックス投資を始めるなら、新NISAを活用するのがおすすめです。
まず、NISAとは少額投資非課税制度のことで、株や投資信託を売却して利益が出た際に課税されない制度です。
投資を行うには証券口座を利用する必要があり、証券口座には課税口座(一般口座と特定口座)とNISA口座(非課税口座)があります。
課税口座で投資をして利益が出ると約20%の税金がかかってしまいますが、NISA口座を使えば利益に税金はかかりません。
| 口座の種類 | 確定申告 | 年間取引報告書 | |
| 課税口座 | 一般口座 | 必要 | 自分で作成 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が作成 | |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 譲渡益が発生した場合は必要 | 証券会社が作成 | |
| NISA口座(非課税口座) | なし | なし | |
特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)の違いは?
源泉徴収は、本来自分で納めるべき税金を証券会社が利益から引いて納めてくれる仕組みです。
源泉徴収ありの場合、確定申告の手間が省けるというメリットがあります。
また、源泉徴収なしの場合、他の証券口座と損益通算をできたり、損失を来年以降に繰り越せるというメリットがあります。
新NISAを使うことで、投資の利益に対する税金がかからないため、長期的な資産形成において大きなメリットを享受できます。
また、インデックス投資に限らず、これから投資を始めたい方は、新NISAを活用することで、利益を非課税で受け取れます。
新NISAの始め方
新NISAの始め方は以下のとおり。
- 証券口座を開設する
- ポートフォリオを決める
- 投資信託を積立購入する
①証券口座を開設する
投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。



クレジットカードで投資信託を積立購入するとポイントが還元されます。
②ポートフォリオを決める
ポートフォリオとは、どれくらいの配分で金融商品の具体的な銘柄へ投資するかという組み合わせを指します。



当サイトで推奨しているポートフォリオは以下の3パターン。
【当サイトで推奨しているポートフォリオ】
- オルカン
- オルカン+債券
- オルカン+インド
※オルカンとは、三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のことです。
詳しくは「新NISAにおすすめのポートフォリオについて解説」をご覧ください。
③投資信託を積立購入する
ポートフォリオを決めたら投資信託を積立購入します。
つみたて投資枠、成長投資枠とは?
新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。
つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。
そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。
なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。
インデックス投資はカモに関するQ&A
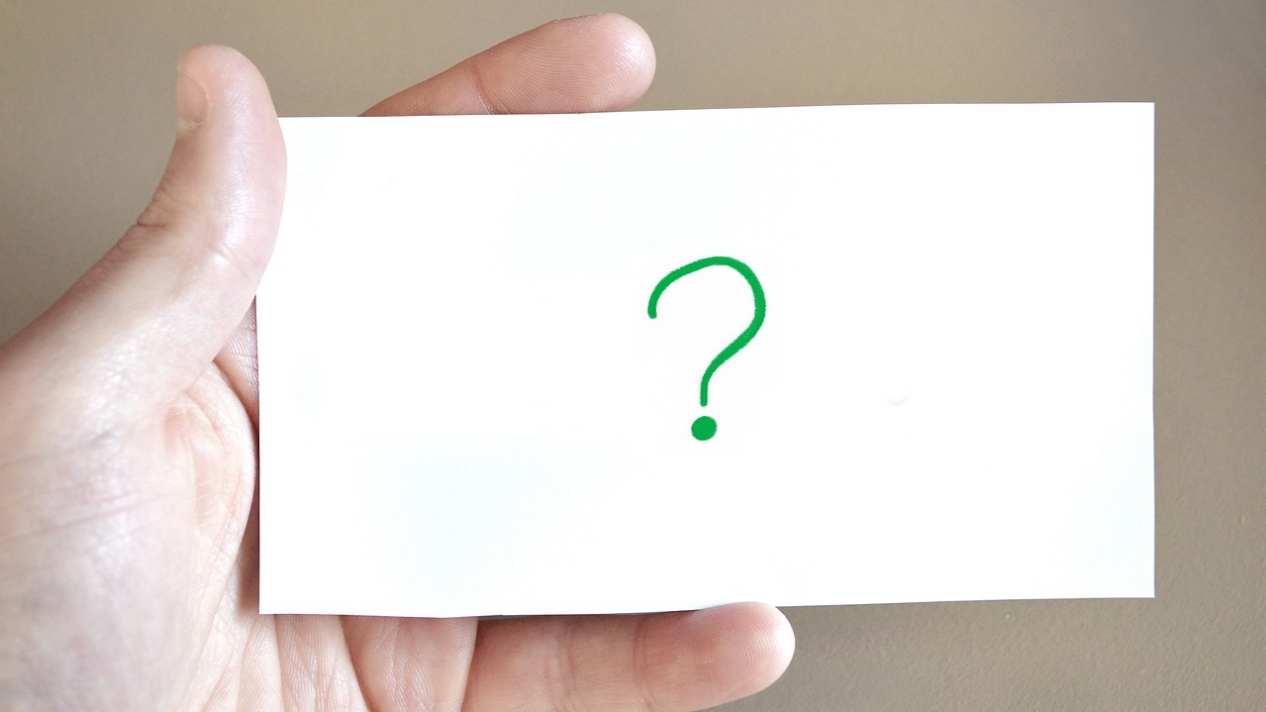
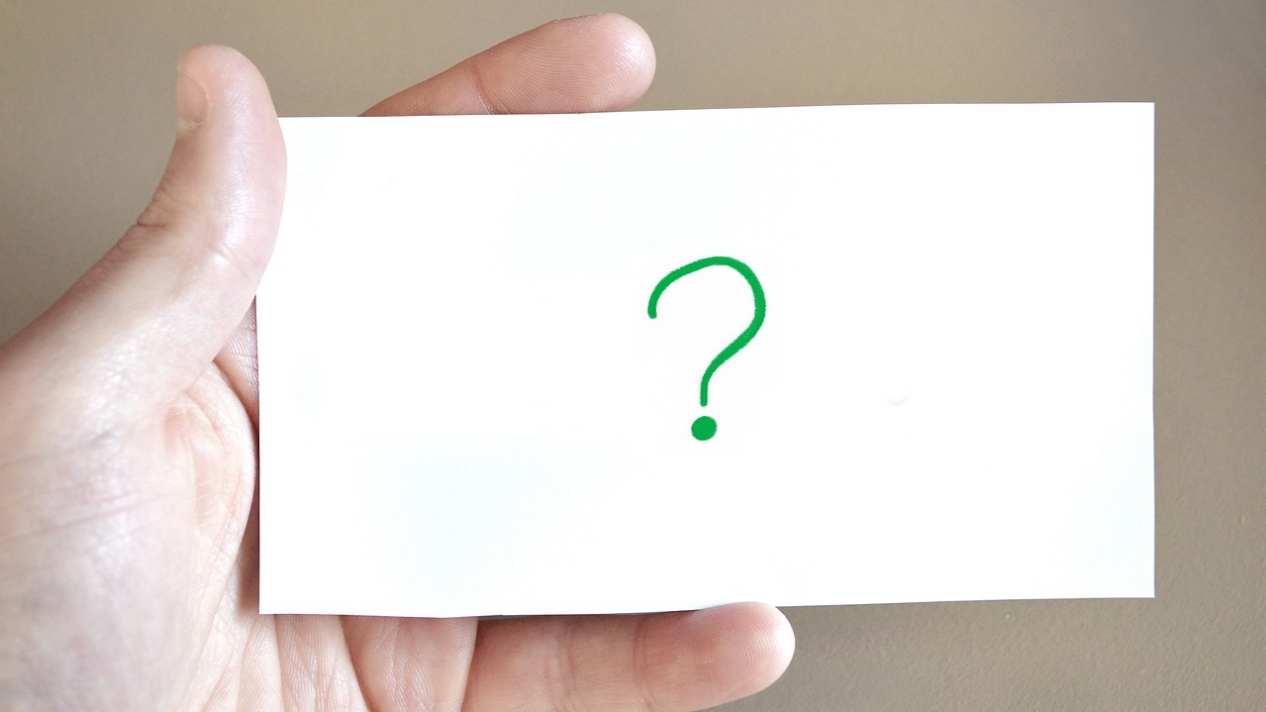
インデックス投資ブームは終わり?
ブームが終わったというよりも、投資手法として定着したと言えます。
市場の動きに合わせて上がり下がりはあるものの、数十年という長い目で見れば、着実に資産を増やしてきました。



「ブームの終わり=投資手法としての終わり」ではありません。
むしろ短期的な流行に振り回されることなく、今後も資産形成の中心的な存在であり続けるでしょう。
インデックス投資は危ない?
インデックス投資も投資である以上、元本保証はなくリスクは存在します。
ただ、広く分散された株式インデックスに投資することで、個別株や短期投機に比べればリスクは抑えられます。
「危ない」というより「リスクを正しく理解すれば安定的」と表現した方が適切です。
インデックス投資は最強?
インデックス投資は最強の投資方法と言えます。
- アクティブ投資より勝率が高い
- 長期的には市場平均並みのリターンを安定して得られる
- 個別銘柄の選択や売買のタイミングを考える必要がない
- 運用コストが低く、積立設定をすれば何もしなくとよい



堅実に資産形成したい人にとっては非常に適しています。
まとめ
今回はインデックス投資はカモについて解説しました。
なお、インデックス投資を始めるには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
| 証券会社 | 特徴 |
  SBI証券公式サイト > >> SBI証券のメリット・デメリットについて解説 | ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 |
  楽天証券公式サイト > >> 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 | 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天カードで投資信託のクレカ積立が可能 |
  マネックス証券公式サイト > >> マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 | 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 |
  三菱UFJ eスマート証券公式サイト > >> 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 | auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 |
